
通常はそうなんですが このような表記を見たことはありませんか?
歎異抄 作者は唯円とされている
なんとも歯切れの悪い表現の仕方ですよね?なぜそうなるのか説明していきたいと思います。
歎異抄の作者と言えば?
通常 唯円! と答える方が大多数だと思いますが
実は唯円とは確定はしていないのをご存知でしょうか?

こういう説明文を見たことはありませんか?
歎異鈔
親鸞聖人没後、聖人の教えとは異なる誤った教えが生じたことを歎き、それを正すために著された書。作者は河和田の唯円という説が有力
有力ということは100%までは確定していないということです。
なぜ歎異鈔の作者が唯円と確定できないのか?
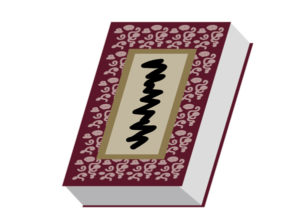
じつは歎異鈔には著者の署名入りの原本が残っておらず、現存する最古のものは 原本ができて200年後 蓮如上人が書き写したもののみだからです。
歎異抄の序文にこのようにあります
先師の口伝の信心とは異なることを歎き
意訳:
親鸞聖人からお聞きした真実の教えとは異なることが説かれており、嘆かわしいことです
ではその歎異した人物とはいったい誰なのか?

歎異鈔 唯円以外の候補者は?


如信上人(1235-1300)
本願寺第二代門主で親鸞聖人の孫 幼少から20歳頃まで祖父である聖人より教えを受けている。父善鸞と関東へ赴く。
覚如上人(1270-1351)
本願寺代三代門主で親鸞聖人のひ孫 親鸞聖人の伝記「親鸞絵伝」「口伝抄」など親鸞聖人に関する書物の執筆がある
等の説が上げられます。
歎異鈔の著者である条件1
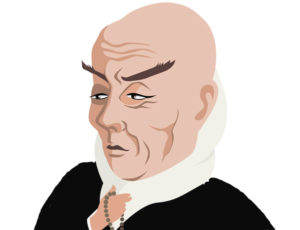
歎異抄の内容を考えると親鸞聖人の言葉を直接聞けた人物です。

語録の部分は日記的な表現もあり 直接 親鸞聖人と接した人物によるものでなければなりません。
歎異抄「序」
故親鸞聖人の御物語の趣、耳の底に留むるところいささかこれをしるす意訳:
今は亡き親鸞聖人から聞かせて頂いた言葉のうち耳の底に残り忘れられないものをここに書き記します
親鸞聖人から直接聞いたということで、親鸞聖人没後に生まれた ひ孫の覚如上人は可能性が低くなります。
歎異鈔の著者である条件2

関東から京都へ来た弟子であること
歎異抄「第二条」
おのおのの十余箇国のさかひをこえて、身命をかへりみずして、たづねきたらしめたまふ御こころざし、ひとへに往生極楽のみちを問ひきかんがためなり。意訳
あなたがたがはるばる十余りの国境を越えて 命懸けで私を訪ねてこられたのは、ただひとえに極楽浄土に往生する道を問いただしたいと言う一心からです。
さらに
歎異抄「中序」
そもそもかの御在生の昔、同じ志にして歩みを遼遠の洛陽に励まし、信を一つにして心を当来の報土にかけし輩は、同時に御意趣を承りしかども、意訳:
思えばかつて、親鸞聖人がおいでになった頃、同じ志をもってはるか遠い京の都まで足を運び、同じ信心を持ってやがて往生する浄土に思いをよせた人々は、ともに親鸞聖人のお心を聞かせていただきました。
はるばる都の親鸞聖人の元を訪ねたという記述があります。
如信上人は義絶された父善鸞と関東に赴きましたが 他の弟子と共に聖人に会いに京の都へ来たとは記録がないので可能性は低くなります。

逆に唯円は1288年の冬の頃、常陸の国 河和田の唯円房という僧侶が上京しましたという記録があります。
親鸞聖人の言葉を直接聞けた人物、関東から来た弟子の二つの条件を満たすのは唯円
彼の名前は歎異抄の本文中にも登場します。
さらに歎異鈔の著者が唯円である根拠
もう消去法でも唯円以外なくなってきましたが まだあります。
歎異抄内での謙譲語の使い方
歎異抄「第九条」
念仏申し候へども、踊躍歓喜ぎのこころおろそかに候ふこと、またいそぎ浄土へまゐりたきこころに候はぬは、いかにと候ふべきことにて候ふやらんと、申しいれて候ひしかば、親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり。意訳:
念仏を称えておりましても、躍り上がるような喜びは湧いてきませんし、また急いで浄土へ参りたいという心が起こってこないのはどう考えたらよいのでしょうかとお尋ねしたところ、この親鸞もなぜだろうと思っていたのだが唯円よ、そなたも同じ思いだったのだなあ。
※唯円よおまえも同じ心であったか!の場面詳しくはこちらで
-

-
歎異抄の名場面 唯円坊 親鸞聖人に極楽浄土に関する疑問をぶつける
歎異抄の名場面 第九条より 歎異抄は門徒たちの間で広がった異説や間違った解釈を正すために唯円が書いたとされる親鸞語録ですが、この九条は他の内容と趣が異なり唯円から親鸞聖人へ問いかける文章になっています ...
続きを見る
「~と、申しいれて」現代語訳で「~とお尋ねしたところ」と謙譲語になっています。
この文章には著者から親鸞聖人へ対しての敬意はありますが、著者から唯円への敬意がありません。
もし著者が質問者の唯円とは別人物であったら、著者から唯円への尊敬語があるはずです。

歎異鈔の著者が唯円で確定できない理由

これでなんで唯円と確定できないの?
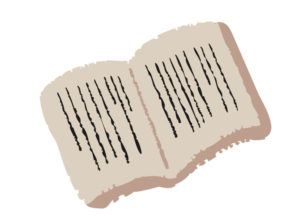
繰り返しますが状況証拠は揃っていますが原本が残っておらず、作者の署名がないから確定ができないのです。
非常に歯がゆいです。

…という問題ではありませんね^_^;
-

-
歎異抄の名場面 親鸞聖人!お念仏で本当に浄土へ行けるのですか?
歎異抄の名場面 親鸞聖人!お念仏で本当に浄土へ行けるのですか? 歎異抄第二条より 親鸞聖人が東国を離れて年月が過ぎると、聖人がいないのをいいことに独自の説を唱えたり、曲解するものが現れ本当にお念仏だけ ...
続きを見る