浄土真宗の法事の進行の一例
法事の時施主は何をすればいいのでしょうか?
もちろんお客さんではないのですから司会進行やお参りの準備をしなくてはいけません。こちらは浄土真宗の法事の進行の一例です。
他の宗派でも正信偈の唱和や御文章(お文)の拝読がないだけでほぼ同じです。
僧侶を玄関で迎え控えの間にお招きする

玄関で出迎えていきなり仏前ではなく衣を脱ぎ着できる控えの間にお通しします。
住宅事情もありますので別室がベストですが仏間で着替えてもらい、その間親族は他の部屋で待機し、着替え終わったタイミングを見計らって仏間に集合でもよいと思われます。
タイミングを見てロウソク、線香の用意をする

適当な時間にろうそく、線香に火を灯します。あまり早いと途中で消えてしまうのでタイミングを考えて行いましょう。僧侶任せにするご家庭も多いようですが、本来おうちの方がお参りの用意をします。
焼香(回し香炉)をする時は火種を用意しお盆に香炉と香合を載せておきます。焼香のはじまりはお寺によって異なりますので事前にご相談ください。
年忌法要の会式の挨拶

準備が整ったら参拝者続いて僧侶にに所定の座についてもらい、施主が会式の挨拶をします。挨拶が終わったら僧侶に読経のお願いをします。
法事の開始の挨拶一例(さらりと)
※浄土真宗の法事は故人を供養する場ではないということを念頭に置き「冥福を祈る」や「故人の霊」など教義に相応しくない言葉は使わないように注意しましょう。
本日はお多用中にもかかわらず、お集まりいただきましてありがとうございます。
ただいまから(続柄+故人名)の〇回忌の法要を執り行いたいと思います。
〇〇寺様お勤めをよろしくお願いいたします。
※法事の開始の挨拶一例(親戚や知合い多し)
〇〇寺様にはお多用のところ(続柄+故人名)釈〇〇(法名)の〇回忌の法要にお越しいただきありがとうございます。
本日は有縁の方々と共に仏法のご縁に遭わせていただきますこと、重ねて感謝申し上げます。それでは〇〇寺様お勤めをお願いいたします。
浄土真宗の法事 読経開始
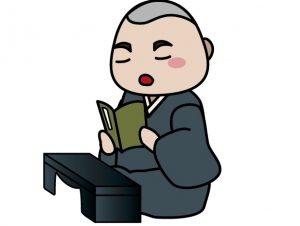
お寺様によってお勤めされる法事のお経の種類は異なりますが、正信偈は全員で唱和し読経中に焼香となったら施主から順に手際よく行います。
浄土真宗の焼香の作法です
・焼香台の少し前で軽く頭を下げる
・お香を本願寺派は1回、大谷派は2回押し頂かないでそのまま香炉にくべます
・合掌礼拝(間違いやすいですが焼香の後に合掌礼拝です)
・少し下がって軽く頭を下げます。
読経が終わると御文章の拝読や法話があるので聴聞します。

法話が終わったら僧侶へお礼の挨拶を述べて法事は終了です。
お斎があればその旨を告げ、移動などの準備をします。
※法事の終わりの挨拶一例
〇〇寺様丁重なるお勤めと法話を頂きましてありがとうございました。皆様におかれましては本日はご多用中にもかかわらず、お参りと御供えを頂きまして誠にありがとうございました。
おかげさまで(父母などの続柄)(故人名)釈〇〇(法名)の〇回忌の法要も終えることができました。これにてお開きとさせていただきたいと思います。なお心ばかりの品をご用意致しておりますので是非お待ち帰りください。
(お斎がある場合はその旨をアナウンスする)
ちょっと小難しく終わりの挨拶
本日はご〇〇寺様に丁重なおつとめを頂き また仏法のご法縁に遭わせていただき誠にありがとうございました。
また皆様方には本日の法事のご案内を申し上げましたところ、ご多用中にもかかわらず お参りいただきましてありがとうございました。
有縁の方々と共に仏法に遭わせて頂く法要をつとめることが出来ましたのも 阿弥陀様のお慈悲のおかげと感謝する次第です。
本日はお参りいただきましてありがとうございました。
(お斎や引き物の箇所は共通)
浄土真宗の法事 気を付けたい点

・法事は故人の追善供養のためのお参りではなく、亡き人をご縁に仏前に一族が集まりお念仏の教えを味わう場
・仏前のロウソク線香の準備を僧侶まかせにしない
・法事の進行は僧侶まかせにせずに施主が行う
・挨拶の際、草葉の陰、冥福を祈るなど浄土真宗の教義とは反する文言を入れない
以上参考になれば幸いです。